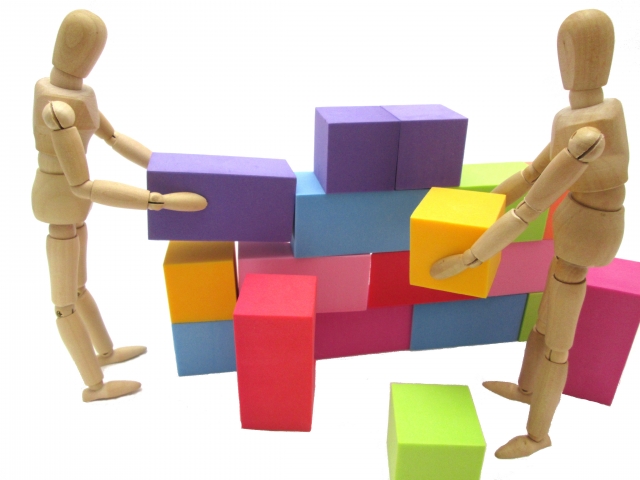新たに取得した土地に、塀や壁を設置したいと考えている方はいませんか?
または、これまで住んでいた土地に塀や壁を設置して、プライバシー保護を強化しようと考えている方もいるかもしれません。
しかし、塀や壁を設置するためにはいくつかのルールが存在します。
ご近所とのトラブルを招かないためにも、費用や高さのことも事前にしっかりと考えておきましょう。
今回は、境界線に塀や壁を設置するケースとしてお話を進めていきます。
境界はトラブルが起きやすい!?
「土地の境界を巡ってトラブルになってしまった」という話はよく聞くものです。
例に挙げるなら、土地の売買によるトラブルです。
土地の売買は金銭にかかわるものですので、ささいな境界のズレでも見過ごすわけにはいきません。
ときには、売却しようとしていた土地の境界線があいまいで、取引自体がなくなってしまうことも考えられます。
そして、境界トラブルとしてよく起こりやすいのが、塀や壁の設置によるものです。
「境界に塀や壁を新たに設置する」、あるいは「古くなった塀や壁を取り壊し新たなものを設置する」などのケースでは、改めて確認したら境界線がズレていたということもよくある話です。
また、前もって何の話もなく、いつのまにか土地の境界に高さのある塀や壁が建てられていたら、たとえ自分の土地ではなかったとしてもいい気はしませんよね。
これまで良好な関係を築いてきたお隣さんとの仲が、境界に塀や壁を作ることで険悪な雰囲気になるのは避けたいものです。
できるならお隣さん同士お互い納得いく形で、塀や壁の建設を進めていきたいですね。
高さのある塀や壁で目隠し!設置しなければいけない決まりがあるの?
お隣との境界線に塀や壁を設置する目的としては、目隠しの要素が大きいと思われます。
たしかに、障壁となるものが何もない状態だと、視線が気になることも多いでしょう。
プライバシーが保たれていないことで、ストレスを感じてしまうこともあるはずです。
この目隠しについては、民法でも定められていることをご存知でしょうか。
民法235条によると、境界線から一メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しをつけなければならないという規定がなされております。
また、窓又は縁側だけでなく、ベランダも含まれます。
このように、塀や壁を設置したい、したくないにかかわらず、上記のような条件に当てはまれば設置しなければならないのです。
層考えると、この条件が当てはまるケースがほとんどではないでしょうか。
民法で定められていることとはいえ、プライバシー保護の観点からも納得できる規定ですよね。
この規定を守るためには、塀や壁の設置は有効な方法と言えます。
ある程度の高さがある塀や壁を設置すれば、気になる視線を遮ることができるでしょう。
塀や壁を設置する前に!隣地境界線を確認しよう!
塀や壁を設置する前に、まずは境界線について知っておきましょう。
土地には、目に見えなくても境界線が存在しています。
境界線があることで、自分の所有している土地がどの範囲なのかを把握することができるのです。
確認すべきは隣地境界線です。
隣地境界線とは、土地と土地の境目が示された線のことを指します。
塀や壁を設置するときは、隣地境界線を基準にすることが多いでしょう。
隣地境界線を確認するためには、まず境界標を見つけてください。
境界標とは、土地の角に当たる部分に設置されているはずです。
もし、境界標が見つからない場合は、地積測量図や道路図を頼りに新しい境界標を設置しましょう。
地積測量図は法務局で、道路図は市区町村役場で確認できるはずです。
隣地境界線をしっかりと確認できたら、塀や壁を設置する準備をしていきます。
塀や壁を設置するためには、費用や高さなどについて決まりごとがありますので、次章からその点について確認していきましょう。
隣地境界線上に塀や壁を設置する!費用や高さに決まりはある?
隣地境界線に塀や壁を作るには、二つの方法があります。
一つ目は、隣地境界線の上に塀や壁を設置する方法です。
この方法の場合、自分の敷地だけではなく、隣家の敷地まで影響が及びますので、設置前にしっかりと話し合いを設けておくと、のちのトラブルを防ぐことができるでしょう。
まず、費用についてのお話しです。
この方法の場合、敷地をまたいでの塀や壁の設置となりますので、費用も共同で負担することになります。
塀や壁の所有権も共有になるということですね。
所有権が共有になるということは、その後の修理費用なども両者が負担することになるということを頭に入れておきましょう。
高さについてはお互いが納得できる形で決めていきます。
しかし、そこで意見が整わなかった場合は、民法上の「板塀、竹垣その他これらと似た材料のもので、2メートルまで」という制限の中でなら設置が許されることになります。
できればお互い納得した上で設置を進めていくためにも、自分だけの主張を押しつけるのではなく、お互いの意見を取り入れていきましょう。
自分の敷地内に塀や壁を設置するケース
次に、隣地境界線に塀や壁を作る二つ目の方法として、自分の敷地内に塀や壁を設置するケースです。
所有している敷地内のことになりますので、何でも自由に決めることができます。
しかし、自由に決められるからといって、常識の範囲を超えるような塀や壁はおすすめできません。
「色や形が奇抜すぎる」「あまりにも高さがある」など、隣家の所有者が不快に思われるようなものは設置しないようにしましょう。
隣家とのトラブルを避けるためには、自分の敷地内に塀や壁を設置する場合でも、事前に確認や報告をしておくと良いでしょう。
ここで、注意しなければならないことがあります。
それは、自分の敷地内に塀や壁を設置するということは、所有者は自分以外誰もいないということです。
つまり、責任は自分一人で負わなくてはいけないのです。
塀や壁は、修繕だけではなく取り壊しの際も費用は発生しますので、その点については心にとどめておいてください。
塀や壁の高さはどれくらいがおすすめ?
ここまで境界線に塀や壁を設置するためのポイントについて、いくつかお話ししてきました。
目隠しとしての働きを担ってくれる塀や壁ですが、どれくらいの高さを設置するのがいいのでしょうか。
いくらプライバシーを守りたいといっても、塀や壁は高ければいいというわけではありません。
塀や壁が高すぎると、圧迫感を与えてしまいますし、場合によっては日の光が届かない場所も出てきてしまうかもしれません。
一般的に選ばれている高さとしては、180センチに設定することが多いようです。
なぜかというと、日本人男性の平均身長が170センチ程度なので、プラス10センチと考えておけば、見た目のバランスをとりながら、視線も気になることが少なくなるためです。
しかし、一般的に180センチが選ばれているといっても、土地の形状により多少の前後は出てくると思います。
最終的には、敷地境界線付近の状態や形状、またお隣さんの意見も参考にしながら設置すると、後悔することがないでしょう。
塀や壁の設置は自分だけの意見で決めない!
境界線に塀や壁を設置するときは、自分だけではなく、敷地所有者全員が納得したうえで話を進めていきましょう。
今後もトラブルなく過ごしていくために、自分以外の意見も参考にすることをおすすめします。
費用や高さについても頭に入れておいてくださいね。
境界に設置する塀や壁は高ければいいというものではありません。
全体的なバランスも考えながら、後悔しない選び方でプライバシーを守っていきましょう。